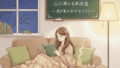本日もご訪問いただきありがとうございます。
【七五三】いつ、何をする日?
由来や年齢ごとの意味、千歳飴の秘密まで分かりやすく解説
 11月になると、神社で晴れ着をまとった可愛らしい子どもたちの姿を目にする機会が増えます。日本の秋の風物詩ともいえる「七五三」は、子どもの健やかな成長を願う、家族にとって非常に大切な節目です。
11月になると、神社で晴れ着をまとった可愛らしい子どもたちの姿を目にする機会が増えます。日本の秋の風物詩ともいえる「七五三」は、子どもの健やかな成長を願う、家族にとって非常に大切な節目です。
しかし、「なぜ3歳、5歳、7歳にお祝いするの?」「男の子と女の子で違いはある?」「千歳飴って、どうして長いの?」といった、その背景にある深い意味や歴史については、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな七五三にまつわるあらゆる疑問に答えるため、その起源となった平安時代の儀式から、現代におけるお祝いの仕方、そして親として知っておきたいマナーまで、詳しく丁寧に解説します。七五三への理解が深まれば、お子様やお孫様の成長を祝う気持ちも、より一層感慨深いものになるはずです。
🎍 この記事で分かること
- ✔ 七五三の由来となった3つの儀式とその意味
- ✔ 「数え年」と「満年齢」どちらで祝うべきか
- ✔ 親の服装や初穂料など、お参りのマナー
- ✔ 千歳飴に込められた親の願い
七五三とは?子供の成長を祝う日本の伝統行事
11月15日に行われる理由
七五三が11月15日に行われるようになったのには諸説ありますが、江戸幕府第5代将軍・徳川綱吉が、息子の徳松の健康を祈ってこの日にお祝いをしたことが始まり、という説が有力です。また、旧暦の15日は二十八宿の「鬼宿日(きしゅくにち)」にあたり、鬼が宿(家)にいるため外出しない方が良いとされる日で、何事をするにも吉日とされたことも理由の一つです。現在では、11月15日にこだわらず、10月から11月にかけての週末や吉日に行うのが一般的です。
「数え年」と「満年齢」どちらで祝う?
本来は、生まれた年を1歳とする「数え年」で祝うのが伝統でしたが、現在では生まれた日を0歳とする「満年齢」で祝う家庭が主流です。どちらで祝っても間違いではありません。お子様の成長の様子や、兄弟姉妹と一緒にお祝いするタイミングなどを考慮して、各家庭で柔軟に決めるのが良いでしょう。
年齢ごとに見る、七五三の由来と儀式の意味

七五三の起源は、医療が未発達で子どもの死亡率が高かった平安時代に、無事に成長できたことを感謝し、さらなる長寿を願って行われた3つの儀式にあります。
3歳「髪置きの儀(かみおきのぎ)」:男女共通
平安時代、3歳までは病気予防のために髪を剃る習慣がありました。3歳の春になると、それを終えて髪を伸ばし始める儀式が「髪置きの儀」です。白髪になるまで長生きできるように、という願いが込められています。
5歳「袴着の儀(はかまぎのぎ)」:男の子
男の子が初めて正装である袴を着用し、幼児から少年へと成長したことを社会的に示す儀式です。世界の中心に立てるようにと願いを込めて碁盤の上に立ち、吉方を向いて儀式を行ったとされています。
7歳「帯解の儀(おびときのぎ)」:女の子
女の子が、それまで使っていた付け紐を解き、大人と同じように幅の広い帯を初めて結ぶ儀式です。幼児から少女へと成長した証であり、社会の一員として認められるという意味合いがありました。
【完全ガイド】七五三当日の流れとお参りのマナー
親や兄弟の服装はどうする?
主役である子どもよりも格を抑えるのがマナーです。子どもが和装なら親も和装(訪問着や色無地など)、子どもが洋装なら親も洋装(スーツやワンピースなど)と、格を合わせると統一感が出ます。父親はダークスーツ、母親はセレモニースーツや上品なワンピースが一般的です。
ご祈祷の受け方と初穂料の相場
神社でのご祈祷を希望する場合は、事前に予約が必要か確認しておきましょう。謝礼である「初穂料(はつほりょう)」は、のし袋に入れて納めるのが丁寧です。金額の相場は5,000円~10,000円程度で、神社によっては金額が決まっている場合もあります。のし袋の表書きは「御初穂料」とし、下には子どもの名前をフルネームで書きます。
七五三の象徴「千歳飴」に込められた深い願い

七五三の縁起物である千歳飴は、江戸時代に浅草の飴屋が「千年」という言葉にちなんで、「長く生きられるように」と売り出したのが始まりとされています。その特徴的な細長い形は子どもの長寿を、紅白の色は縁起の良さを表しています。鶴や亀、松竹梅といった長寿を象徴する絵柄が描かれた袋に入れられ、親から子への「健やかに、長く生きてほしい」という切なる願いが込められているのです。
📝 まとめ:成長への感謝と未来への願いを込めて

七五三は、単なる儀式や写真撮影のイベントではありません。その根底には、かつて子どもの生存率が低かった時代から続く、「ここまで無事に育ってくれてありがとう」という親の深い感謝と、「これからも健やかに、幸せに生きていってほしい」という未来への切なる願いが込められています。
その歴史や一つひとつの儀式の意味を知ることで、お子様の晴れ姿がより一層愛おしく、感慨深く感じられるはずです。ぜひ家族みんなで、子どもの成長を祝い、感謝する、温かい一日にしてください。