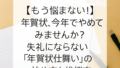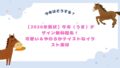“書く”がもっと楽しくなる!僕がブログを続けるために実践しているネタ探しの習慣と伝わる文章術
本日もご訪問いただき、ありがとうございます♪
はじめに:かつて僕も「何を書けばいいか分からない」と途方に暮れていた

突然ですが、ブログを書いている(または、これから書きたいと思っている)あなたは、こんな風に悩んだことはありませんか??
- 「よし、ブログをやるぞ!と意気込んだはいいけど、何を書けばいいか分からない…」
- 「最初の数記事は書けたけど、もうすっかりネタ切れ…」
- 「頑張って書いたのに、全然読まれていない気がする…」
分かります、分かります。何を隠そう、これ全部かつての僕自身のことなので…(^_^;)
ブログを始めた当初は、書きたいことが溢れているように感じていたのに、気づけばパソコンの前でうんうん唸るばかり。しまいには、「自分には発信できることなんて何もないんじゃないか…」なんて、ネガティブな気持ちになってしまうこともありました。
つい先日のことなんですが、追い打ちをかけるような事件もありました。パソコンのデータが飛んで、書きかけの記事が全部消えかけたんです!
うわーー!、、、?、!😱
ディスクトップにはごみ箱だけしか無い状態…。あの時の絶望感は、今思い出してもヒヤッとします(苦笑)。幸い、システムの復元機能という、まさに「ド○えモンのタイムマシンみたいな機能」のおかげで事なきを得たのですが、一時は本当にブログをやめようかと思いました。
でも、そんな僕でも、なんだかんだ言いながらブログを書き続けています。それはなぜか?
答えはシンプルで、「書くこと」が自分自身の成長に繋がり、何より「楽しい」からです。そして、その楽しさを見つけるまでには、ちょっとした「コツ」や「習慣」があったんです。
この記事では、かつての僕と同じように悩んでいるあなたに向けて、僕が実践している「ネタ探しの習慣」と「伝わる文章術」を、余すところなくお伝えしたいと思います!この記事を読み終える頃には、「なんだ、もっと気軽に書いていいんだ!」「自分にも書けることがあるかも!」と、書くことへのハードルがぐっと下がっているはずです。ぜひ、最後までお付き合いくださいね!
📝 Part 1:もうネタ切れに悩まない!日常が宝の山に変わる「ネタ探し」の習慣
ブログ継続の最大の壁、それは「ネタ切れ」ですよね…。でも、安心してください。ネタは「探す」ものではなく、日常に「気づく」ものです。ここでは、僕が実践している4つの習慣を紹介します!
すべての源泉!日常の「なぜ?」をメモする習慣 📱
ネタの神様は、日常のふとした瞬間に舞い降ります。その瞬間を逃さないために、僕が一番大事にしているのが「メモ」です。
例えば、
- 「マスクしてるとメガネが曇るの、どうにかならないかな?」
- 「恵方巻って、なんで黙って食べるんだっけ?」
- 「このアプリ、面白いけどどういう仕組みなんだろう?」
こんな、本当に些細な「疑問」や「感情が動いたこと」を、すかさずスマホのメモアプリに記録します。ポイントは、「記事にしよう」と気負わずに、ただのつぶやきとして記録すること。

ちなみに、僕が以前書いた「メガネの曇り止め」の記事も、元はと言えば「マスクでメガネが曇る😣」という、ただの個人的な悩みからでした。この「個人的な悩み」こそが、同じ悩みを持つ読者の共感を呼ぶ、最高のネタの原石になるんです。
“好き”を深掘りする!エンタメやガジェットは最高のネタの宝庫 💻
あなたが「好き」なものは、他の誰かにとっても魅力的なテーマです。僕の場合、それは漫画やアニメ、そして新しいガジェットです。
ただ、「この漫画、面白かった!」で終わらせるのはもったいない!そこから一歩進んで、
- 「なぜ、このキャラクターの言葉に心を動かされたんだろう?」
- 「この作品のどこを、まだ観ていない友人におすすめしたいだろう?」
- 「このガジェットの機能、自分の生活のどこで一番役立っているだろう?」
というように、自問自答してみるんです。そうすることで、単なる感想が、あなた独自の視点が加わった「レビュー記事」や「解説記事」に進化します。「ちはやふる」の記事で競技かるたの面白さを語ったり、「iPhoneの便利機能」を紹介したりしたのも、この「好きの深掘り」から生まれています。
読者の「困りごと」に寄り添う視点 🤔
自分の「好き」や「悩み」だけではありません。視点を少し広げて、周りの人々の「困りごと」に耳を傾けてみるのも、素晴らしいネタ探しの方法です。
例えば、僕が受けた「玉掛けクレーン講習」。あの記事は、「これから講習を受ける人って、どんなことが不安かな?」と考えたのがきっかけでした。「実技試験って難しいのかな?」「どんな準備が必要なんだろう?」と、過去の自分が知りたかった情報をまとめることで、未来の誰かの役に立つ記事が生まれます。
友人や同僚との雑談の中に、「〇〇で困ってるんだよね」という言葉が出てきたらチャンス!また、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトを眺めて、世の中の人がどんなことに疑問を持っているのかをリサーチするのも、ネタの宝庫を発見する有効な手段ですよ。
【まとめ】ネタ探し習慣化のための3つのステップ 🚀
ここまで紹介した習慣を、今日から実践できる3つのステップにまとめました。まずはここから始めてみませんか?
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メモアプリを決める | いつでもどこでも、1秒で起動できるものがベスト! |
| 2 | 1日1つ、感情が動いたことを記録する | 「面白い」「なぜ?」「困った」など、一言でOK。 |
| 3 | 週に1度、メモを見返して”育てる” | メモに一言、関連情報や思ったことを追記してみる。 |
✍️ Part 2:「伝わる」から「面白い」へ!読者が前のめりになる文章術
ネタが見つかったら、次はいよいよ「書く」フェーズです。でも、ただ情報を並べるだけでは、読者は途中で飽きてしまいます。ここでは、読者がまるであなたと会話しているかのように、スラスラと読んでしまう文章術のコツを紹介します。
結論から書かない!「共感」から始める導入の魔法 ✨
学校では「結論から書きなさい」と習ったかもしれませんが、ブログは少し違います。僕が意識しているのは、「共感から始める」こと。
この記事の冒頭のように、「~なこと、ありませんか?」と読者の状況を代弁したり、自分の失敗談を先に語ったりすることで、「そうそう、分かる!」「この人も同じなんだ」と、読者との間に見えない橋を架けることができます。この橋が架かれば、読者はあなたの言葉を「自分ごと」として、真剣に聞いてくれるようになります。
まるで会話!「ですます調」に”ちょい足し”する3つの工夫 😄
丁寧な「ですます調」は基本ですが、それだけだと少し堅苦しい印象になることも。僕は、丁寧さを保ちつつ、会話のようなライブ感を出すために、3つの”ちょい足し”を意識しています。
① 問いかけを入れる
「~だと思いませんか?」と文末で問いかけることで、読者に考えるきっかけを与え、一方的な説明になるのを防ぎます。
② 感情を乗せる
嬉しい時には「(≧∇≦)」、困った時には「(^_^;)」、驚いた時には「😱」。顔文字や絵文字、そして感嘆符(!!)を効果的に使うことで、文章に体温が宿ります。
③ 擬音語・擬態語で臨場感を出す
PCの復旧シーンでの「うぃーーーん(・。・)」のように、音や様子を言葉にすることで、読者はその場の光景をより鮮明にイメージできます。
読者を飽きさせない!リズムを生むデザインのコツ 🎨
どんなに良い内容でも、文字がぎっしり詰まっていると、読者は読む前に疲れてしまいます。文章の「中身」と同じくらい、見た目の「デザイン」も重要です。
- 2~3行に一度は改行して、余白を作る。
- 重要なポイントは太字にする。
- 3つ以上の項目は、箇条書き(リスト)にする。
- 特に伝えたいメッセージは、囲み枠で強調する。
- 関連する画像や、簡単な図解を挟んで、視覚的な変化をつける。
これらの小さな工夫が、文章にリズムを生み、読者が最後まで心地よく読み進めるための道しるべになります。
難しいことを”面白く”する比喩と例え話 💡
専門的な内容や、少し複雑な話をするときほど、比喩や例え話の出番です。僕がシステムの復元機能を「ド○えモンのタイムマシン」と例えたように、読者がすでに知っている身近なものに例えることで、難しい内容もすっと頭に入ってきます。
常に「このテーマに全く詳しくない友人に話すとしたら、どう説明するかな?」と自問自答することが、分かりやすい例え話を見つける秘訣かと思います。
⚙️ Part 3:継続は力なり!僕が愛用するライティング効率化ツール
ここまでネタ探しや文章術について語ってきましたが、「言うは易し、行うは難し」ですよね。最後に、僕がブログを書き続ける上で、実際に頼りにしているツールをいくつか紹介します。便利なツールに頼ることで、書くことのハードルはもっと下がります!
1. メモアプリ:Google Keep
シンプルで動作が軽く、思いついた瞬間にサッとメモできるのが魅力です。スマホとPCで自動同期されるので、どこでもアイデアを書き留められます。
2. 構成作成ツール:XMind (マインドマップ)
記事全体の構成を考えるときに使っています。中心にテーマを置き、そこから枝葉を伸ばすように見出しや内容を書き出していくと、頭の中が整理されて、話の抜け漏れがなくなります。
3. 文章校正ツール:オンラインの日本語校正サービス
書き終えた文章をコピー&ペーストするだけで、誤字脱字や「ら抜き言葉」などをチェックしてくれます。完璧ではありませんが、公開前の最終チェックとして使うと、文章の質がぐっと上がります。
これらはあくまで一例ですが、自分に合ったツールを見つけることで、ライティングはもっと効率的に、そして楽しくなりますよ!
さいごに:完璧じゃなくていい。まずは”今の自分”を発信することから始めよう 💪

ここまで、僕なりのブログ継続のコツをお話ししてきましたが、一番伝えたいのは「最初から完璧な記事なんて書かなくていい」ということです。
僕の過去記事を読み返すと、「うわ、この文章分かりにくいな…」「もっとこう書けばよかった…」と反省することばかりです(笑)。でも、それでいいんだと思っています。
大切なのは、今の自分の知識や経験、そして熱量を、精一杯の言葉で発信してみること。発信を続けることで、新しい知識が増えたり、考えが整理されたり、そして何より、自分の書いた記事が誰かの役に立った時の喜びを知ることができます。
この記事が、あなたの「書きたい」という気持ちを少しでも後押しできたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
一緒に、ブログでの発信を楽しみましょう!最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!✨
【おまけ】ライティングの参考になるおすすめ書籍3選 📚
ルールに従い、最後に僕が文章を書く上で影響を受けた本を3冊だけ紹介させてください。
1. 新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング
「面白い文章」とは何か、その構造を分かりやすく解説してくれる一冊。すぐに実践できる具体的なテクニックが満載で、僕の文章構成の考え方の基礎になっています。
2. 20歳の自分に受けさせたい文章講義
文章は「リズム」が大事だということを教えてくれた本。読者が心地よく読める文章とは何か、そのための推敲の技術を学べます。

3. 沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—
漫画形式でWebライティングの基礎からSEOまでを学べる画期的な本。ストーリーが面白く、楽しみながらWebで「読まれる」ための文章術が身につきます。